脳・からだ・こころ -SBS Archive- No.1
バーチャルリアリティ 技術で解き明かすスポーツ選手の「技」と「心」(後編)
リスクを取れる人がスポーツ競技に向く!?
Toshitaka KIMURA & Makio KASHINO
2017.4.26

反応する人、反応しない/できない人
—スポーツの経験者と未経験者では、VRを用いた計測で動きや生体応答に違いがあったということですが、そのほかにも明らかになったことがあるのでしょうか?
木村: ええ、興味深かったのが、頭めがけて飛んでくるビーンボールに対する反応です。実験では、ときどきビーンボールを混ぜているのですが、経験者の場合は、頭を後ろにそらしてうまく回避する動きが見られるんですね。ところが、未経験者はうまく避けられなかったり、間に合わなかったり、動きがまちまちなのです。そもそも、未経験者は動き出し自体が遅いので、時間的に間に合わないということもあるのだと思います。ところが意外にも、まったく反応を示さない人がいることがわかりました。
—デッドボールを受けても、微動だにしないってことですか?
木村: はい。もちろんVRですから、実際に球が当たるわけではないのですが、通常はヴァーチャルだとわかっていても思わず反応してしまうものです。そもそも、回避動作というのは生物として当然備わっている機能だと思われるのですが、意外にも反応しない、あるいはできない人がいる。しかも、それは年齢や性別には関係ないように見受けられます。
柏野: これは本当に意外でしたね。最近、転んでも手をつかず顔から地面にぶつかって怪我をする小学生が増えているという話を聞くことがありますが、この実験結果は、これまで生得的な反射、つまり生まれながら持っている機能だと思っていたことが、実はそうではなく、もしかすると学習による部分が大きいということを示しているのかもしれません。あるいは、反射的な反応は個人差が非常に大きいのかもしれない。脳科学的に非常に興味深いテーマです。
木村: 回避行動が生得的な機能だとしても、高度に発達した人間社会の中で、回避するような動きをすることが少なくなって、機能が失われつつあるのかもしれませんね。そういったことも、この研究を通じて明らかにしていきたいと考えているところです。
スポーツに向く人の性質が明らかに!?
柏野: もう一つ、投球の中にビーンボールを混ぜることの面白さは、意思決定のジレンマに関わるその人の性質をあぶり出す点にあります。というのも、球を打つためには、当然、前に踏み込まなければならないわけですよね。ところが、踏み込めば、デットボールを受ける可能性がある。リスクをとるのか、ベネフィットをとるのかの選択を迫られるわけです。しかも、その選択を誤ると、大怪我をするかもしれない。それでも、ベネフィットを取ろうと踏み込めるかどうか、これはその人の性質に大きく関わります。
現在、脳科学では盛んに意思決定に関する研究が行われていますが、リスクをとった結果、身の危険に晒されるといった重大な帰結をもたらすような状況下での実験はほとんど行われていません。そういった意味でも、この研究は意義深いと思っています。
しかもそれが、考え抜いた判断ではなく、潜在脳機能という無意識的な反応を調べている点に新規性があります。「頭ではわかっていても思い通りに動けない」、「勝手に身体が動作してしまう」という部分を担う潜在脳機能の特徴がわかれば、それぞれの人に合ったスポーツ技術の向上に役立てられると思います。
木村: 潜在脳機能のレベルでリスクを取るタイプの人か、慎重派かといったタイプを判別できれば非常に面白いですね。本人は慎重派だと思っていても、無意識のレベルでは意外にもリスクを取るタイプだということもあり得るかもしれません。
柏野: プロの選手でもさまざまですね。過去にデットボールを受けたトラウマからプロテクターをつけないと打席に立てない人もいるし、デッドボールで骨折したことがあっても果敢に攻めるタイプの人もいる。もっとも、大活躍している選手というのは、多かれ少なかれリスクを取れるからこそ結果を残せているわけですが。
あるいは、最初に思わずのけぞるような内角高めの球が飛んできたとして、その次の球に対してどう反応するのかも、人によってかなり違うはずです。大震災などもそうですが、1000年に一度程度しか起こらないと言われても、甚大な被害を目の当たりにすれば、やはり誰しもがなんらかの影響を受けますよね。ただ、その捉え方はやはり人によって違う。リスクに対する判断というのは、統計に基づく合理的なものなどではなく、それぞれの個人が持っている資質に大きく左右されると思います。
木村: 極端に言えば、あまりに慎重なタイプの人はスポーツ競技には向いていないかもしれませんね。いくらバットコントロールが上手くても、踏み込めなければ打てないですから。ただ、それも二段階あって、潜在脳機能と顕在脳機能では、タイプが違うかもしれない。そうした、潜在と顕在の乖離も、VRによる計測で明かにしていきたいと思っています。
—今後は、さらに何か機能を追加されるのですか?
木村: はい。現在は球が当たった時にカーンと打音が鳴る程度ですが、今後はよりリアリティを高めた音を出したり、球が当たったときのバットの感覚をリアルに再現したりしたいと考えています。また、途中で消えるような球や変化球に対する反応、音のタイミングを変えることによる反応などを調べるために、さまざまに条件を変えたり、チューニングしたりしていく予定です。さらには、プロのアスリートが何をどのように見ているのかといった、一流選手のすぐれた「技」や「心」の本質、その背後にある脳情報処理のメカニズムの解明にまで踏み込んでいきたい。やることはたくさんあります。
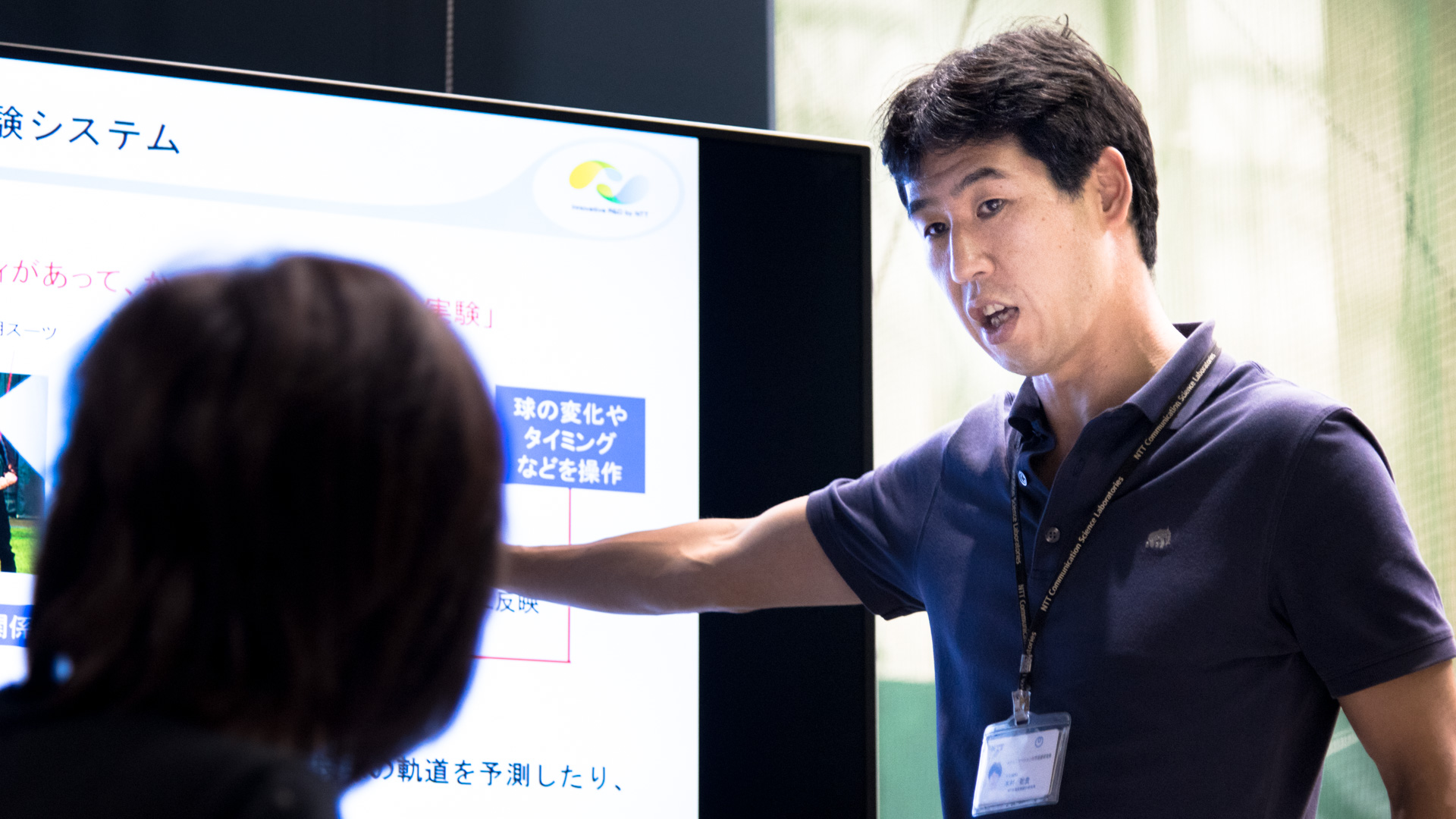
身体をうまく操るためのコツを示したい
—ところで、木村さんご自身もさまざまなスポーツをなさるそうですね?
木村: 小学生のときから野球をやっていて、中学校まで軟式野球部に所属していました。ところが一転、高校ではラグビー部に入部したんですね。テレビドラマの「スクールウォーズ」に影響を受けたのもありますが、ちょうど私が中学生の頃に、早稲田大学が社会人を破って日本一になり、学生ラグビーが大旋風を巻き起こしたのを見て、やってみようと。それから、私は仙台出身なのですが、親が北海道の出身ということもあって、物心がついた頃からスキーをやっています。
—同じスポーツでも、それぞれ特徴が違うのでしょうか?
木村: 全然違いますね。野球とラグビーは対人スポーツですが、相手との関係性で発揮する能力が変わってきます。どちらもいわゆる駆け引きの面白さがありますが、野球のほうは一つひとつプレーが途切れるので準備や“読み”がとても大事、ラグビーは時々刻々と変わる状況を瞬時に判断し、対応する能力が求められますね。一方、スキーは、基本的には一人で楽しむものなので、いかに自分の身体をうまく使うかということに意識を集中します。それぞれ問題意識が違う部分もあり、それが今の研究にも生かされているように思います。
—研究もずっとスポーツ関連なのですか?
木村: はい、もともと運動に興味があったので、学部の頃から運動に関わる研究をしていました。最初は、身体のエンジンとも言うべき筋肉について研究していて、どうしたらうまく筋肉を鍛えられるかとか、いかにして疲れない身体を手にいれるかといったことに興味がありました。一方で、その頃から、筋肉を鍛えることと身体をうまく操ることはイコールではない、という問題意識も持つようになり、大学院からはそういった研究をしてきました。ただ、当時は実験室実験が主流で、スポーツそのものの研究を進めることはなかなかできなかった。最近になってウェアラブル機器の進展や柏野さんとの出会いもあり、ようやく現在のような研究ができるようになったというわけです。
柏野: 出会ったのはかなり前だけど、具体的に動き出したのは3年前くらいだよね?
木村: そうですね。もともとは、柏野さんは聴覚のご専門で、僕は運動が専門で接点はなかったのですが、お互いスポーツ好きなので雑談をしているうちに、とある研究会に加わることになったのがきっかけです。
柏野: あれは確かにエポックメイキングな研究会でしたね。そもそも、スポーツ科学と脳科学では、これまで接点がほとんどなくて、言葉が通じないような状況でしたから。そうした中で、もともと木村さんが師事していた東京大学の中澤公孝先生を中心に、この前までメンバーだった井尻哲也君らとともに研究会を立ち上げた。そこから本格的に研究がスタートしました。
また、VRもウェアラブルデバイスも機械学習も、ここ数年で格段に進歩を遂げていて、実際に実験に使えるものになってきたことも研究を加速させてきた大きな要因と言えます。
木村: さらに、2020年の東京オリンピックの開催が決まったこともあり、我々への期待も大きくなっていますね。その期待に応えるためにも、ただ脳機能を解明するだけでなく、次のステップとして、実際のトレニーニングに活用できるようなシステムを開発していきたいと考えています。
そもそも、スポーツの経験者と未経験者で動きが違うのは、身体に動きが染みついるか、いないかにあるわけですよね。じつはそれは脳が覚えているかどうかによるわけですが、ではどうやって脳にそのコツを覚え込ませることができるのか。単にトップアスリートの動きのビデオを見たところで真似できないように、脳の機能や身体の動きがそれぞれ解析できたところで身体の動きの巧みさを手に入れることはできません。我々は、その部分に切り込んでいくためのアプローチに取り組もうとしています。
—具体的にどのようなアプローチを考えているのですか?
木村: たとえば、球を投げるとき、肩や腕の筋肉だけで投げているわけではなくて、身体全体を使っているわけですね。いいピッチャーになればなるほど、全身の筋肉をうまく連携させて、コントロールしながら投げている。そのすべての動きを真似することはできませんが、主要な筋肉の組み合わせのパターンを抽出することができれば、コツがつかめるようになるかもしれない。つまり、重要な部分に的を絞ってコントロールする術がわかれば、上達するための近道を示すことができるのではないかと考えています。そのための方法論やシステムの開発についても、まさに今、模索しながら取り組んでいるところです。

(取材・文=田井中麻都佳)
Profile

NTT コミュニケーション科学基礎研究所 スポーツ脳科学プロジェクト


編集・ライター/インタープリター。中央大学法学部法律学科卒。科学技術情報誌『ネイチャーインタフェイス』編集長、文科省科学技術・学術審議会情報科学技術委員会専門委員などを歴任。現在は、大学や研究機関、企業のPR誌、書籍を中心に活動中。分野は、科学・技術、音楽など。専門家の言葉をわかりやすく伝える翻訳者(インタープリター)としての役割を追求している。趣味は歌を歌うことと、四十の手習いで始めたヴァイオリン。大人になってから始めたヴァイオリンの上達を目指して奮闘中。

